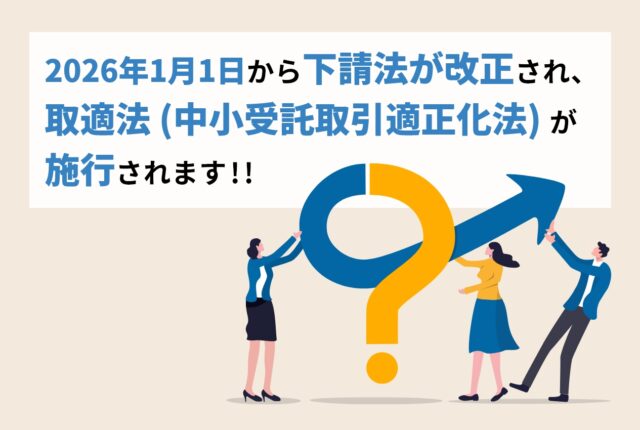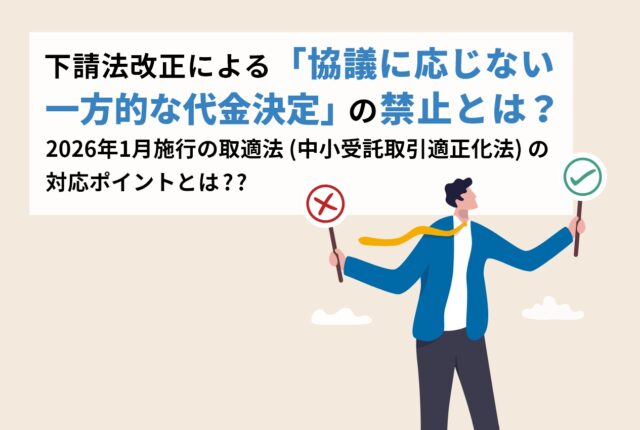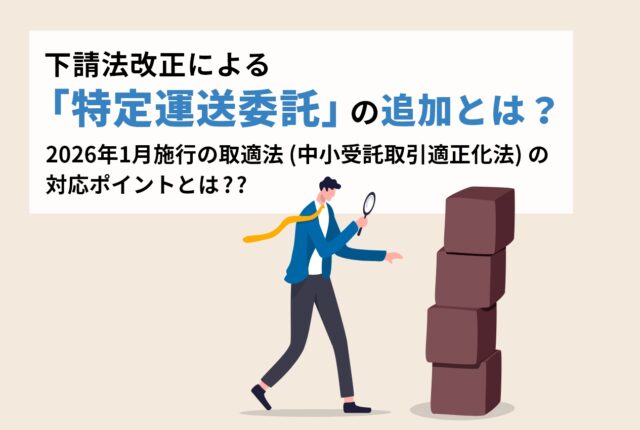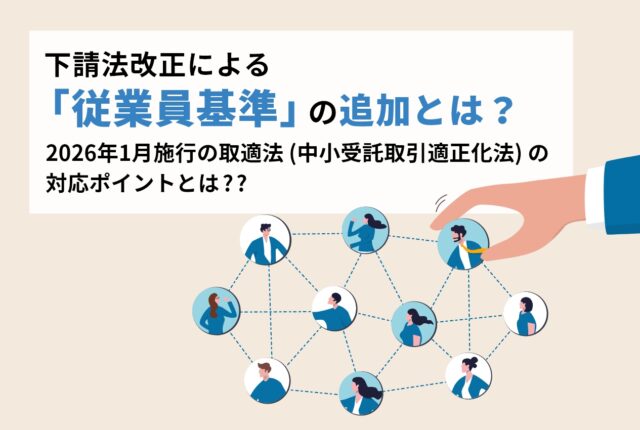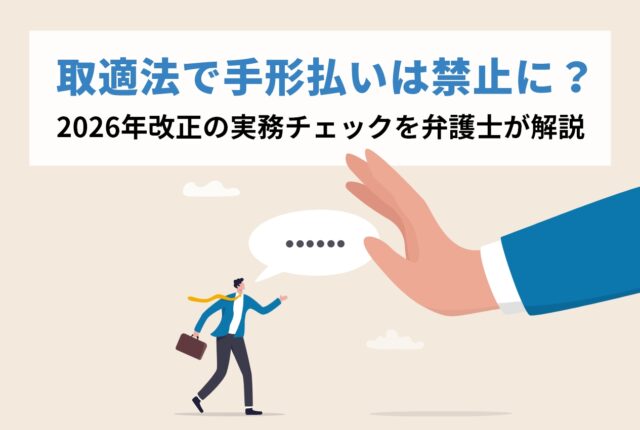目次
よくある相談
- 製造を委託した金型を下請事業者に預けたまま、数年間発注していません。このような場合でも下請法違反になることはありますか?
- 自社が所有している金型を下請先に保管してもらっていますが、保管料を支払っていません。これも「不当な経済上の利益の提供要請」(下請法違反)にあたる可能性がありますか?
- 下請先から「保管場所が手狭なので金型を引き取ってほしい」と言われていますが、次の発注時期が未定の場合、どのように対応するのが適切でしょうか?
下請法とは?
下請法とは、「下請代金支払遅延等防止法」の略称で、下請取引の公正化や下請事業者 の利益保護を目的としており、中小企業政策の重要な柱となっている法律です。
下請法では、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるため、①親事業者の義務や②親事業者の禁止行為を定めています。
親事業者の禁止行為ー不当な経済上の利益の提供要請(下請法4条2項3号)
下請法では、親事業者が下請事業者に対して優越的な地位を濫用することを防ぐため、複数の禁止行為を定めています。その中の一つが、「不当な経済上の利益の提供要請」(下請法4条2項3号)です。
この規定は、親事業者が自己の利益のために、下請事業者に金銭や役務などの経済的な負担を強いることにより、下請事業者の利益が不当に害されることを防止することを目的としています。
言い換えれば、親事業者が自社の都合で下請事業者に経済的な負担を押しつける行為が、この禁止行為の典型です。
公正取引委員会は、以下のような行為を「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するおそれがあるものとして例示しています。
問題となる行為類型:
- 協賛金の要請
- 従業員の派遣
- 知的財産権の無償の譲渡・許諾
- システム利用料等の徴収
- 無償での技術指導、試作品等の製造等
- 金型の図面の無償提供
- 金型の無償保管
このうち、⑦金型の無償保管は、近年特に問題視されている行為です。
金型の無償保管と下請法違反
製造業の取引では、製品の生産が終了した後も、親事業者が下請事業者に金型を保管させ続けるケースが多く見られます。
一見すると「取引上の慣行」に見えるこの行為ですが、長期間発注がないにもかかわらず保管料を支払わない場合には、下請法が禁止する「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するおそれがあります。
実際に、令和5(2023)年以降、公正取引委員会は金型の無償保管に関して複数の企業に対して勧告を実施しています。
また、公正取引委員会が公表している「下請法Q&A(質問46)」でも、金型等の保管が下請法違反となるケースを明示的に紹介しています。
具体的には、部品等の製造を委託し、その製造に用いる型等を下請事業者に保管させている場合において、親事業者が部品等の発注を長期間行わない等の事情があるにもかかわらず、保管費用を支払うことなく下請事業者に型等を保管させたときは、不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれがあるとしています。
金型の無償保管が下請法違反となる4つの類型
それでは、「親事業者が部品等の発注を長期間行わない等の事情」とは、どのようなケースをいうのでしょうか?
公正取引委員会のウェブサイト(「下請法Q&A(質問46)」)では、以下の4つの類型を紹介しています。
ケース①部品等の発注を長期間行わない場合
金型等を用いて製造する製品の発注を1年間以上行わないにもかかわらず、下請事業者に当該金型等を無償で保管させていた事例
ケース②下請事業者が型等の廃棄や引取り等を希望している場合
下請事業者から金型の廃棄や引取り等の希望を伝えられていたにもかかわらず、引き続き、下請事業者に当該金型を無償で保管させていた事例
ケース③親事業者が次回以降の具体的な発注時期を示せない場合
金型を用いて製造する製品について今後1年間の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにもかかわらず、引き続き、下請事業者に当該金型を無償で保管させていた事例
ケース④型等の再使用が想定されていない場合
木型等を用いて製品が製造された後、当該木型等を改めて使用する予定がないにもかかわらず、引き続き、下請事業者に当該木型等を無償で保管させていた事例
金型の無償保管で問題が生じやすい3つの実務ポイント ― 下請法違反を防ぐために注意すべき点とは?
ポイント①製造が終了した時点で保管の要否や保管料を検討すること
下請法上は、最終発注製品の製造が終了した時点から保管終了までの期間について、親事業者が保管費用を支払うことが基本的な考え方となります。もっとも、製造終了後に「とりあえずそのまま置いておいてほしい」と保管を続けるケースがあります。保管を続ける場合は、期間・費用・責任分担を明確化することが必要です。
ポイント②下請事業者からの“廃棄・引取り希望”を放置
下請事業者が「倉庫が手狭」「保管が負担」として廃棄や引取りを求めているにもかかわらず、親事業者が対応を先送りするケースがあります。下請法上は、こうした要望を無視して無償保管を継続させる行為が、「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する可能性があります。希望を受けた段階で速やかに協議し、処理方針(引取り・廃棄・費用負担)を決めることが求められます。
ポイント③“今後の発注予定”が不明確なまま保管を続けている
今後1年間の発注予定や再使用の可能性が具体的に示せないにもかかわらず、「また使うかもしれない」として無償で保管を続けるケースがあります。特に、モデルチェンジ・製品ライン終了などで再使用が実質的に想定されない型については、違反リスクが高まります。次回発注の見通しがたたない場合、保管の必要性について検討するタイミングです。
弁護士法人かける法律事務所における取適法対応のサポート
2026年1月の改正により、取適法の規制対象や禁止行為は、広がります。発注者・受注者の双方にとって「どこまで対応が必要か」「契約書や社内体制をどう変えるべきか」を早めに整理しておくことが重要です。
弁護士法人かける法律事務所では、以下のようなサポートを提供しています。
① 契約書・取引スキームのリーガルチェック
- 改正後の「従業員数基準」や「特定運送委託」の追加などを踏まえ、自社が規制対象となるかを判定。
- 委託契約書や基本契約の内容を精査し、禁止行為(協議に応じない一方的な価格決定、手形払等)に抵触しない条項へ修正。
- 実際の取引スキームが取適法に沿っているかを検証し、改善提案を行います。
企業のメリット:
- 不意に「法違反リスク」を抱えることを防ぎ、安心して取引を継続できます。
② 価格交渉・価格転嫁の実務サポート
- コスト上昇分を価格に反映するための「協議の進め方」について、法的観点からアドバイス。
- 発注者側企業には、受注者からの協議要請にどう対応すべきか、社内ルール作成を支援。
- 下請代金の引下げやコスト上昇における引上げ価格の検討・プロセスについて、法的観点からアドバイス。
企業のメリット:
- 法に沿った適正な交渉ができ、長期的に安定した取引関係を構築できます。
③ 社内研修・コンプライアンス体制の構築
- 経営層・購買担当者向けに「取適法対応セミナー」を実施。
- 違反事例や実務上のリスクを共有し、現場担当者が実践できるチェックリストを提供。
- 法改正に合わせた社内マニュアル・ガイドラインの整備もサポート。
企業のメリット:
- 現場の担当者レベルまで法改正の理解を浸透させ、違反リスクを未然に防止できます。
独占禁止法・下請法対応は、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
紛争やトラブルを未然に防止し、健全な企業体質をつくって、経営に専念できる環境を整備するためにも、顧問契約サービスの利用について、是非、一度、ご検討ください。
顧問契約サービスでは、独占禁止法・下請法対応もリーズナブルに、かつ、迅速に対応できます。コンプライアンス研修(独占禁止法・下請法)も引き受けています。