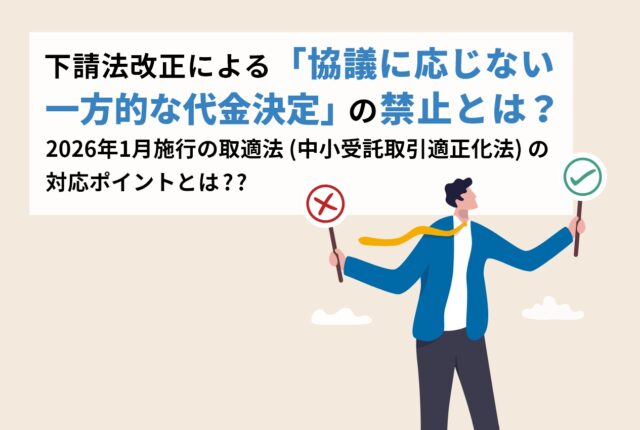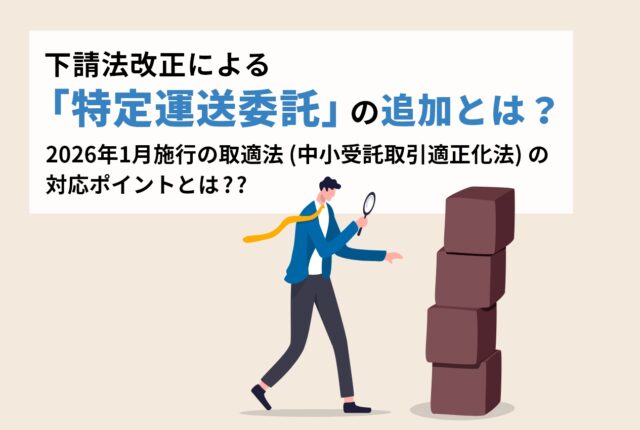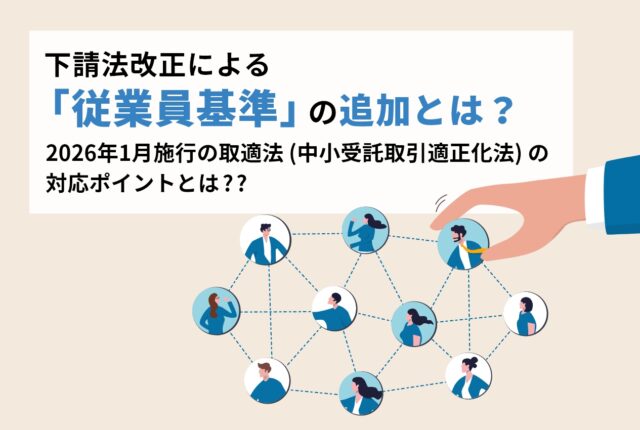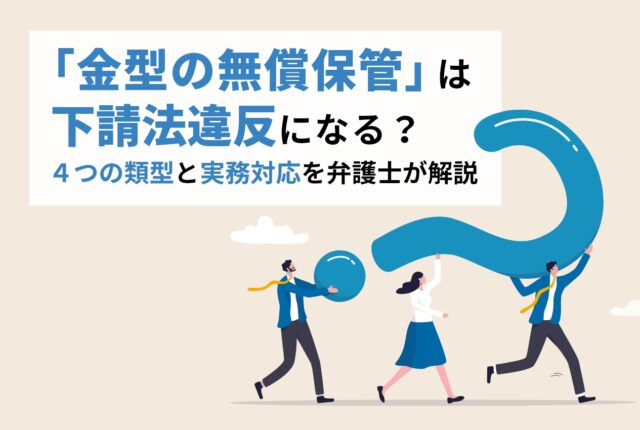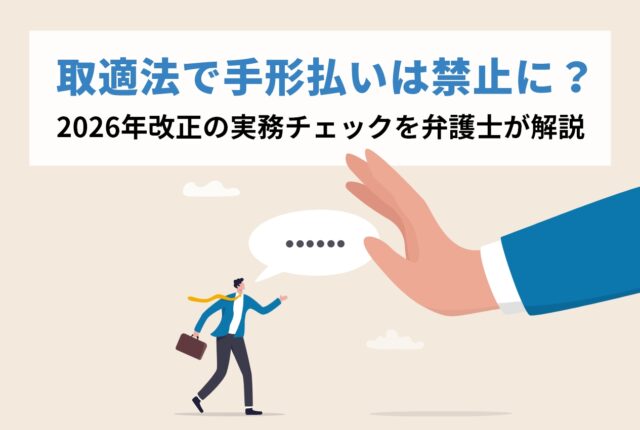目次
よくある相談
- 下請法が改正されると聞きました。どのような内容ですか?
- 下請法の改正によって、新たに、どのような取引が規制の対象となりますか?
- 手形払いが禁止されるって、本当ですか?
下請法(下請代金支払遅延等防止)とは?
下請法とは、「下請代金支払遅延等防止法」の略称で、下請取引の公正化や下請事業者 の利益保護を目的としており、中小企業政策の重要な柱となっている法律です。
下請法では、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるため、①親事業者の義務や②親事業者の禁止事項を定めています。
2026年1月1日から下請法が改正され、取適法(中小受託取引適正化法)が施行されます!~法律の名称や用語の変更~
近年、労務費・原材料費・エネルギーコストが急激に上昇する中で、発注者と受注者が対等な関係を築き、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁を定着させる、いわゆる「構造的な価格転嫁」の実現が求められています。
そのため、多段階にわたる取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくため、下請法が改正され、2026年1月1日から取適法(中小受託取引適正化法)が施行されることになりました。
この改正に伴い、下請法に関連する法律の名称や用語が以下のとおり、変更されます。
- 下請代金支払遅延等防止法(略称:下請法)
→製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法) - 下請代金
→製造委託等代金 - 親事業者
→委託事業者 - 下請事業者
→中小受託事業者
取適法の改正内容~適用対象の拡大~
① 適用基準に、資本金基準に加えて、従業員基準が追加されます!!
下請法では、取引内容に応じて、親事業者(委託事業者)と下請事業者(中小受託事業者)の資本金基準によって、その適用の可否が決定されます。
例えば、製造委託では、親事業者(委託事業者)の資本金が3億円を超える場合、下請事業者(中小受託事業者)の資本金が3億円以下の場合に下請法が適用されることになります。
もっとも、実際には、事業規模が大きいにもかかわらず資本金が少額である会社や、減資を行うことによって下請法の適用を回避するケースがあったり、下請法の適用を回避するため、受注者側に増資を求める発注者が存在するケースもありました。
そのため、取適法では、資本金基準に加えて、従業員基準が追加されることになり、資本金基準では下請法の対象にならなかったケースでも、取適法では、従業員基準によって取適法の対象となるケースがあり、適用対象が拡大されました。
- 従業員基準の具体例①(製造委託の場合)
委託事業者300人超 → 中小受託事業者従業員300人以下 - 従業員基準の具体例②(情報成果物作成・役務提供委託【プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るものを除く】)
委託事業者100人超 → 中小受託事業者従業員100人以下
② 対象取引に「特定運送委託」が追加されます!!
下請法では対象取引が、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」の4種類に限定されていましたが、取適法の施行によって対象取引に「特定運送委託」が追加されます。
「特定運送委託」とは、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託をいい、具体的には、事業者が販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品等について、その取引相手方に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいいます。
- 具体例1:
物品の販売事業者が、その物品の販売先に対する運送を他の事業者に委託する場合 - 具体例2:
物品の製造を請け負う事業者が、その物品の製造の発注者に対する運送を他の事業者に委託する場合 - 具体例3:
物品の修理を請け負う事業者が、その物品の修理の発注者に対する運送を他の事業者に委託する場合 - 具体例4:
情報成果物の作成を請け負う事業者が、その発注者に対する運送を他の事業者に委託する場合
③ 対象取引となる製造委託の対象物品に金型以外の型等(木型、治具など専ら物品の製造に用いる物品)が追加されます!!
製造委託とは、物品を販売し、又は物品の製造を請け負っている事業者が、規格や品質等を指定して、他の事業者に物品の製造や加工等を委託することを言いますが、この製造委託の対象となる物品に、金型だけでなく、木型、治具など専ら物品の製造に用いる物品も追加されました。
取適法の改正内容~禁止行為の追加~
① 協議に応じない一方的な代金決定が禁止されます!!
下請法では、委託事業者の禁止行為として、受領拒否や代金の支払遅延、代金の減額などが規定されていました。
これに対し、取適法では、新たに「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止行為として追加されることになりました(取適法5条2項4号)。
この背景には、コストが上昇しているにもかかわらず、委託事業者が、中小受託事業者と協議を行わずに価格を据え置いたり、上昇分に見合わない価格を一方的に決めてしまうといった問題があります。
こうした行為は、価格転嫁を妨げ、中小企業に過大な負担を押しつける要因となってきました。そのため、適切な価格転嫁が行われる取引環境を整備する必要があるとの考えから、新たに禁止行為として位置づけられたものです。
つまり、委託事業者が中小受託事業者から価格協議の要請を受けながら、協議に応じなかったり、必要な説明を行わない場合には、取適法に違反することになります。
違反行為の具体例:
- 中小受託事業者が代金額の引き上げについて協議を求めたが、これを無視して、協議に一切応じなかった。
- 委託事業者が代金額の値下げを要請するに際して、中小受託事業者がその説明を求めたものの、具体的な理由や根拠を一切説明することなく、代金を引き下げた。
② 手形払等が禁止されます!!
下請法では、発注した物品等の受領日から60日以内で定められる支払期日までに下請代金を支払わない場合、支払遅延として委託事業者の禁止行為に該当します。
もっとも、60日以内に支払われる場合でも、支払手段として手形等を用いることによって、発注者が受注者に対して資金繰りに関する負担を求める商慣習があり、中小受託事業者の保護のために、取適法では、手形払等を禁止することになりました(取適法5条1項2号)。
ここで禁止される支払手段は、①手形の交付に加えて、②電子記録債権や一括決済方式についても、支払期日までに製造委託等代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難である場合も含まれます。
つまり、手形払等は、製造委託等代金の支払遅延に該当することとなるため、委託事業者は、手形払等を行うことが禁止されます。
2026年1月施行「取適法」への対応ポイント~企業・購買担当者向け~
① 適用範囲の拡大に注意
これまで下請法は「資本金基準」で適用範囲を決めていましたが、今後は「従業員基準」が新たに導入されます。これにより、資本金が少なく対象外だった企業でも、従業員数によっては規制対象となるケースが増えることになります。
さらに、今回の改正では対象取引の範囲も広がります。新たに「特定運送委託」が追加され、製造・販売・修理した物品等を運送する委託も対象になります。また、製造委託の対象物品に、金型以外の型(木型、治具など)も含まれるようになります。
対応策:
- 自社や取引先が規制対象になるかどうか、資本金だけでなく従業員数や取引内容も踏まえて確認することが必要です。
- 契約書の内容や発注方法についても、適用範囲を前提に見直しを進めましょう。
② 一方的な価格決定の禁止
原材料費や人件費の高騰にもかかわらず、発注者が協議に応じずに価格を据え置いたり、不当に低い価格を一方的に決める行為は、新たに禁止行為として明確に規制されます。
対応策:
- 受注者側は、コスト上昇分を価格に反映できるよう、根拠を資料や数値で示し、協議を求める体制を整えましょう。
- 発注者側は、受注者から協議を求められた場合、根拠や資料をもって対応・説明できる体制やルールを社内で徹底する必要があります。
③ 手形払等の禁止
支払手段として手形払いを利用している場合、手形払いが禁止されることになります。また、手形だけでなく、電子記録債権やファクタリングについても、禁止される場合もあります。
対応策:
- 支払方法を「現金払い・振込払い」に切り替える準備を進めること。
- 発注書や契約書に記載されている支払方法を確認し、禁止行為に該当しないか精査しておきましょう。
弁護士法人かける法律事務所における取適法対応のサポート
2026年1月の改正により、取適法の規制対象や禁止行為は、広がります。発注者・受注者の双方にとって「どこまで対応が必要か」「契約書や社内体制をどう変えるべきか」を早めに整理しておくことが重要です。
弁護士法人かける法律事務所では、以下のようなサポートを提供しています。
① 契約書・取引スキームのリーガルチェック
- 改正後の「従業員数基準」や「特定運送委託」の追加などを踏まえ、自社が規制対象となるかを判定。
- 委託契約書や基本契約の内容を精査し、禁止行為(協議に応じない一方的な価格決定、手形払等)に抵触しない条項へ修正。
- 実際の取引スキームが取適法に沿っているかを検証し、改善提案を行います。
企業のメリット:
- 不意に「法違反リスク」を抱えることを防ぎ、安心して取引を継続できます。
② 価格交渉・価格転嫁の実務サポート
- コスト上昇分を価格に反映するための「協議の進め方」について、法的観点からアドバイス。
- 発注者側企業には、受注者からの協議要請にどう対応すべきか、社内ルール作成を支援。
- 下請代金の引き下げやコスト上昇における引上げ価格の検討・プロセスについて、法的観点からアドバイス。
企業のメリット:
- 法に沿った適正な交渉ができ、長期的に安定した取引関係を構築できます。
③ 社内研修・コンプライアンス体制の構築
- 経営層・購買担当者向けに「取適法対応セミナー」を実施。
- 違反事例や実務上のリスクを共有し、現場担当者が実践できるチェックリストを提供。
- 法改正に合わせた社内マニュアル・ガイドラインの整備もサポート。
企業のメリット:
- 現場の担当者レベルまで法改正の理解を浸透させ、違反リスクを未然に防止できます。
独占禁止法・下請法対応は、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
紛争やトラブルを未然に防止し、健全な企業体質をつくって、経営に専念できる環境を整備するためにも、顧問契約サービスの利用について、是非、一度、ご検討ください。
顧問契約サービスでは、独占禁止法・下請法対応もリーズナブルに、かつ、迅速に対応できます。コンプライアンス研修(独占禁止法・下請法)も引き受けています。