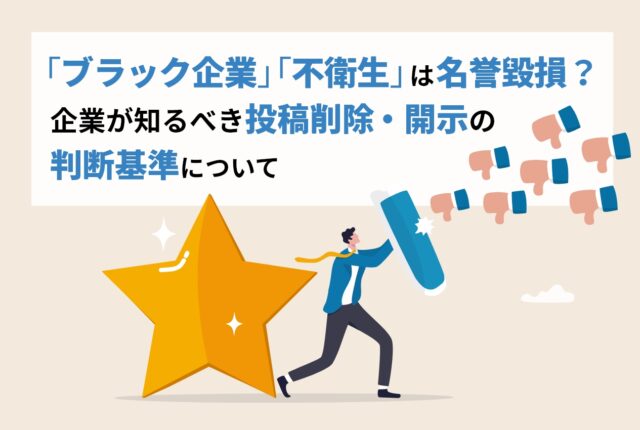目次
よくある相談
- SNSやグーグル口コミで、自社の商品やイメージが低下する投稿が行われている。
- ネット上の掲示板で、自社の労働環境についてネガティブな内容の投稿がされており、今後の採用活動や取引に悪影響を及ぼす可能性がある。
- 企業に対する誹謗中傷について、名誉毀損に当たるかどうかの判断基準を知りたい。
本コラムでは、法人(企業)に対する名誉毀損について、直近の裁判例を紹介しながら、名誉毀損の判断基準を解説していきます。
※名誉毀損の判断基準については、こちらの記事(Q&A<インターネット誹謗中傷対応>「ブラック企業」・「不衛生」は名誉毀損?企業が知るべき投稿削除・開示の判断基準)でも取り上げていますので、是非、チェックしてみてください。
名誉毀損(名誉権侵害)の判断方法
まずは、名誉毀損(名誉権侵害)の一般的な判断方法について、解説をします。
ある表現行為が名誉毀損に当たるかどうかは、大きくいうと、次の2つの判断プロセスによって判断されます。
- その表現内容により対象者の社会的評価の低下があるか
- ( 社会的評価の低下が肯定される場合 ) その表現行為に正当化事由があるか
以下、①社会的評価の低下、②名誉毀損の正当化事由について、それぞれ解説をしていきます。
社会的評価の低下とは?
名誉(名誉権)とは、一般に、個人や法人が外部的に有している社会的評価のことをいい、この社会的評価を低下させる行為が、名誉毀損(名誉権侵害)になります。そのため、ある表現内容について、名誉毀損というためには、特定の対象者(個人や法人)の社会的評価を低下させるものである必要があります。
特定の対象者の社会的評価を低下させる行為であるため、前提として、その投稿が誰に対して言及しているか分からない場合は、特定の対象者の社会的評価を低下させているとはいえず、名誉毀損には当たりません(「同定可能性」の問題)。
※「同定可能性」の問題については、こちらの記事(Q&A<インターネット誹謗中傷対応>名誉毀損における同定可能性について、弁護士が解説します。)で詳細に解説しています。
また、実務上では、社会的評価を低下させる表現について、「事実摘示型」と「意見論評型」に区別されることが一般的です。一般に、「意見論評型」よりも「事実摘示型」の方が名誉毀損が成立しやすいため、この区別は重要なポイントになります。
「事実摘示型」と「意見論評型」の区別ですが、裁判例の考え方としては、表現されている内容について、証拠をもって判断できるかどうかで区別されています。
例えば、「あのお店の料理は最低レベルである」という内容だと、「料理のレベルが最低」かどうかは、あくまで個人がどう思うかの話であって、証拠でもって判断できることではないため、「意見論評型」になります。
一方で、「あの会社では残業代が払われない」という内容であれば、従業員の勤怠管理に関する資料(就業規則、タイムカード、賃金台帳等)によって判断できるため、「事実摘示型」になります。
名誉毀損の正当化事由(違法性阻却事由)とは?
ある表現行為によって、特定の対象者の社会的評価の低下が認められる場合でも、実務上、一定の正当化事由が肯定される場合には、名誉毀損には当たらないことが認められています。
正当化事由として、実務上もっともよく問題になるのが、「真実性の抗弁」(違法性阻却事由)です。
「真実性の抗弁」とは、以下の①~③の各要件をすべて満たす場合に、表現行為の違法性が阻却されるというものです。この抗弁が認められる場合、その表現行為は名誉毀損には当たらないことになります(「事実摘示型」の場合を念頭に置いた説明です)。
- 公共の利害に関する事実に係ること
- 専ら公益を図る目的でなされたこと
- 企重要な部分の内容が真実であること
これらの各要件のうち、法人(企業)に対する表現行為については、実務上、公共利害関連性(要件①)や公益目的(要件②)が肯定されることが多いため、投稿内容が真実かどうか(要件③)によって、名誉毀損の成否が決まる場合が少なくありません。
そのため、名誉毀損を主張する企業側としては、投稿内容が反真実であること(虚偽であること)について、裏付けとなる証拠資料の提出も含めて、主張を準備しておく必要があります。
名誉毀損を肯定した裁判例の紹介
ここまで、一般的な名誉毀損の判断方法を説明しましたが、ここからは、具体的な事例(名誉毀損を肯定した裁判例/否定した裁判例)をいくつか取り上げて、裁判所における判断基準を見ていきます。
名誉毀損を肯定した裁判例①(東京地判令和元年8月20日)
【事案の概要】
転職サイトの口コミ掲示板で、原告(株式会社)の労働環境について、「サービス残業を強要している」等のネガティブな内容の投稿が行われたため、原告が、名誉毀損(名誉権の侵害)を理由に、掲示板の運営会社に対して、発信者情報開示請求を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のとおり述べて、原告に対する名誉毀損を肯定し、開示請求を認めました。
「本件投稿記事2は、「始業前終業後サービス勤務を強要されている。」との事実を摘示するものであるところ、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば、当該記事は、原告において、労働基準法に違反して時間外手当の支払なく超過勤務を命じていると読めるから、読者に原告は労働基準法に違反して労務管理を怠っているような会社であるとの印象を与え、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。」
「他方、本件投稿記事2は、・・・その内容や表現ぶりからして公共の利害に関する事実に係るものであって、公益目的に出たものであると推認することができる。しかしながら、証拠によれば、原告において超過勤務は許可制となっており、残業前に申請をする必要があること、残業時間はタイムカードにより管理されて分単位で時間外手当が支払われていること、平成29年5月に原告が従業員に行った調査でも「サービス残業」は存在しないと回答した者が多く、回答があいまいであった従業員に対して改めて調査した結果もチェックの付け忘れ等によるもので、「サービス残業」の存在を確認することはできなかったことが認められ、そうすると、「サービス勤務を強要されている」との摘示は真実ではない可能性が高いというべきであって、この点で違法性阻却事由の不存在をうかがわせる事情がある。」
「本件投稿記事3は、・・・「成果があげられないと評価されず二ヶ月間成果がでないとクビになる。」との事実を摘示するものであるところ、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば、・・・業務上の成果が上げられないとそれを理由に解雇されると読めるから、読者に対し、原告が解雇権を濫用しているか、そうでないとしても業務上一定の成果が出せないという理由のみで解雇されることがあるとの印象を与えるから、原告の社会的評価を低下させるものというべきである。」
「他方、本件投稿記事3は、・・・その内容や表現ぶりからして公共の利害に関する事実に係るものであって、公益目的に出たものであると推認することができる。しかしながら、・・・証拠によれば、原告の人事評価においては7段階により昇級及び降級の基準が客観的に定められ、一定の期間に営業実績を上げた者や組織貢献度が高い者は昇級していくものの、一定の営業成績に達しない場合等には、これを支店長以下管理職の評定に基づいて順に降級していく仕組みとなっていることが認められ、そうすると、上記のような降級の可能性はあるものの、2か月間成果が上げられないことにより、「クビ」すなわち解雇をされるとの摘示は真実ではない可能性が高いというべきであって、この点で違法性阻却事由の不存在をうかがわせる事情がある。」
【コメント】
本件は、転職サイト上での口コミの事案ですが、原告の社会的評価を低下させることを肯定した上で、正当化事由(違法性阻却事由)があるかという、一般的な判断手法によって判断しています。
正当化事由(違法性阻却事由)の判断においては、公共利害関連性や公益目的は肯定しているため、投稿内容の真実性が争点となっています。
本件では、「始業前終業後サービス勤務を強要されている。」「成果があげられないと評価されず二ヶ月間成果がでないとクビになる。」等の投稿内容が反真実であると判断して、名誉毀損を肯定していますが、就労環境について具体的な事実が指摘されている点が、開示請求が認められたポイントといえます。
すなわち、本件で開示請求側は、投稿内容の反真実を基礎づけるために、「サービス残業(=時間外手当が支払わない超過勤務)が存在しないこと」や「成果を挙げられないことを理由とする解雇はないこと」を主張立証すればよく、勤怠管理や人事評価制度に関する客観的な証拠の提出により、投稿内容の反真実が比較的立証しやすかった事案であるといえます。
名誉毀損を肯定した裁判例②(東京地判令和3年5月31日)
【事案の概要】
インターネット上の掲示板上で、原告(株式会社)の労働環境に関して、社内でのハラスメントや従業員のうつ病に関するネガティブな投稿が行われたため、原告が、名誉毀損(名誉権の侵害)を理由に、掲示板の運営会社に対して、発信者情報開示請求を求めた事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のとおり述べて、原告に対する名誉毀損を肯定し、開示請求を認めました。
「本件各記事は、・・・原告について、「必要な連絡をわざと伝えず、集団で嘲笑」(本件記事1)、「ハラスメントは必要悪らしい」(本件記事2)と摘示するものである。」
「これらの投稿内容に照らすと、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方とを基準とすれば、本件各記事は、原告において、①必要な連絡をわざと伝えないまま、連絡を受けなかった従業員を、他の複数の従業員が嘲笑するといった嫌がらせ行為が見受けられること(本件記事1)、②ハラスメントが必要悪であると評価する従業員が所属し、この状態が是正されていないこと(本件記事2)を認識させ得るものと認められる。そして、原告において、上記のような従業員に対する嫌がらせが行われ、又は、ハラスメントを必要悪として許容する従業員が所属しており、更には、原告が、企業として、これらの問題について適切に指導又は是正することができていないといった認識が伝播すれば、原告の社会的評価が低下することは優に認められる。」
【コメント】
本件の投稿内容ですが、「必要な連絡をわざと伝えず、集団で嘲笑」(本件記事1)、「ハラスメントは必要悪らしい」(本件記事2)という投稿の文言だけを読むと、直接的に何か具体的な事実を指摘している表現方法とはいいづらく、婉曲的・遠まわしな方法でハラスメントの存在に言及している点が、本件事案の特徴といえます。
裁判所は、本件の投稿内容について、その文言だけを読み取るのではなく、その投稿内容がいわんとする事実を汲み取って判断しています。つまり、「必要な連絡をわざと伝えず、集団で嘲笑」(本件記事1)という内容については「必要な連絡をわざと伝えないまま、連絡を受けなかった従業員を、他の複数の従業員が嘲笑するといった嫌がらせ行為が見受けられる」という事実の摘示であると読み取り、「ハラスメントは必要悪らしい」(本件記事2)という内容についても、「ハラスメントが必要悪であると評価する従業員が所属し、この状態が是正されていない」という事実の摘示であると読み取った上で、原告の社会的評価を低下させる事実が摘示されていると判断しました。
本件事案のように、インターネット上の投稿では、その文言だけからは、どのような事実が摘示されているか不明確な場合が少なくありません。その場合でも、名誉毀損を主張する側としては、その投稿内容が真にいわんとするとする内容を探求した上で、具体的な事実を摘示するものと構成できるかどうかを、検討する必要があります。
名誉毀損を否定した裁判例の紹介
名誉毀損を否定した裁判例①(東京地判令和元年12月24日)
【事案の概要】
インターネット上の掲示板上で、原告(株式会社)の担当者の対応に問題があるかのような投稿が行われたため、原告が、掲示板の運営会社に対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のとおり述べて、原告に対する権利侵害(名誉毀損)を否定し、開示請求を認めませんでした。
「本件記事3(「担当者が酷い」、「断るのに苦労した」、「口止めされた」との事実を摘示する投稿)には、知人からの伝聞として、当該知人は契約成立間近まで話を進めたもののやめたこと、具体的な話はできないものの担当者が酷かったこと、実績が少なすぎること、知人は断るのにかなり苦労したこと、担当者について苦情を申し立てた際に、弁護士について言及の上で口止めをされたことなどの記述がある。
これらの記述は、いずれも原告の営業活動についての記述であると理解することができるものの、担当者が酷かったことについては問題点についての具体的な指摘はないし、知人が(原告側との契約締結を)断るのにかなり苦労したとの記述や、担当者について苦情を申し立てた際に口止めをされたことについても、当該知人と原告側との間で何らかのトラブルが存在していたことを前提に、そのトラブルの経過においてあり得る出来事の域を出るものではなく、それ自体が直ちに原告の社会的評価を明らかに低下させるものということは困難である。」
【コメント】
本件の投稿内容(「担当者が酷い」、「断るのに苦労した」、「口止めされた」)について、裁判所は、「担当者が酷かったことについては問題点についての具体的な指摘はない」「当該知人と原告側との間で何らかのトラブルが存在していたことを前提に、そのトラブルの経過においてあり得る出来事の域を出るものではなく」と判断し、原告の社会的評価を低下させるものではないと判断しています。
さきほど説明したように、意見や論評であっても社会的評価を低下させる場合はありえますが、裁判所の傾向として、具体的な事実の摘示を伴わないことを理由として、社会的評価の低下を否定するという判断を行うことがあります。そのため、やはり、投稿の中で具体的な事実が指摘されているかどうかが、名誉毀損の成否を分ける重要なポイントであるといえます。
名誉毀損を否定した裁判例②(東京地判令和元年5月14日)
【事案の概要】
転職口コミサイトで、原告(株式会社)の元在籍者により、原告の入社時の説明に問題があったかのような投稿が行われたため、原告が、サイトの運営会社に対して、発信者情報開示請求を行った事案です。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のとおり述べて、原告に対する権利侵害(名誉毀損)を否定し、開示請求を認めませんでした。
(社会的評価の低下について)
「本件投稿・・・の記載内容のうち、「まず退職時に研修費用が請求される制度は入社前にちゃんと把握して置くべきだと思うし、採用担当者も最終面接などの段階でそのような研修費用請求の制度や研修の内容と金額を明示すべき」との記載部分は、原告が、社員の退職時に研修費用を請求する制度について、入社前に社員に把握させる措置をとっていないとの事実を摘示した上で、かかる制度について、最終面接の段階で採用担当者が説明するなどして入社前に周知すべきであるなどという本件発信者の意見を表明したものといえる。
上記のような事実摘示及び意見の表明から成る本件投稿の内容は、一般の閲覧者がこれを読んだ場合には、原告が、退職時に研修費用を請求する制度について社員が入社する前に説明せず、退職する際に不意打ち的に請求しているとの印象を与え、原告の社会的評価を低下させるものといえる。」
(正当化事由の有無について)
「本件投稿の公共性及び公益性について検討すると、・・・本件ウェブサイトは、転職・就職活動を行う者に、転職先・就職先の候補となる会社に関する情報を提供することを目的として運営されていることが認められ、本件投稿・・・も、本件ウェブサイトを閲覧する転職・就職希望者のために、原告を転職先・就職先候補に選択するか否かを判断するのに役立つ情報を提供する目的によりされたものと考えられるから、本件投稿・・・に公共性及び公益性がないとはいえない。」
「次に、真実性ないし相当性について検討すると、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告では、研修を受講する社員に原告が研修費用を無利子で貸し付け、当該社員が原告に在籍する間はその返還を求めないが、5年以内に退職する場合には、研修費用を60か月で分割した金額に、在籍5年に至るまでの残存期間を乗じた金額の返還を請求する制度(以下「本件制度」という。)を採用していることが認められ、本件各投稿の「回答者」欄に「在籍3年未満」と表示されていること・・・及び本件投稿・・・の投稿内容に鑑みると、本件発信者は、入社後5年以内に原告を退職し、実際に研修費用の返還請求を受け、その際、本件制度について認識しておらず、かかる請求がなされることを予見していなかったものと考えられる。
原告は、本件制度について、社員が入社する前に複数回にわたり説明していたと主張し、これに沿う証拠を提出しているが、本件発信者は、「回答者」欄に「在籍3年未満、退社済み(2015年以降)」と表示されていることや、投稿内容に、原告に在籍することは「最初1~2年はある程度勉強にはなる」旨、自身が2年以上在籍していたことをうかがわせる内容を記載していることから、平成24年ないし平成25年ころ原告に入社したものと考えられるところ、同時期に、原告が、本件制度について入社前に説明していた事実や、説明の内容及び程度を裏付ける的確な証拠はないことからすれば、本件投稿において摘示された事実(原告が、本件制度について、入社前に社員に把握させる措置をとっていないとの事実)が真実でないとまでは認められず、仮に真実でないとしても、同事実を真実と信じることについて相当な理由がないと認めることもできない。
そして、これらの摘示事実を前提とした本件発信者の意見表明部分についても、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものとは認められない。」
【コメント】
本件事案でも、まず、本件投稿による社会的評価の低下を肯定した上で、正当化事由の有無について判断するという一般的な手法で判断しています。そして、正当化事由(違法性阻却事由)の判断においては、公共利害関連性や公益目的を認めた上で、投稿内容の反真実性が問題となっています。
そして、本件の投稿内容の反真実性の判断では、投稿者の在籍時期がポイントになっています。すなわち、裁判所は、原告の会社において、本件制度(5年以内に退職した場合は貸し付けた研修費用の返還を求められる制度)が採用されていることを認める一方で、投稿者が入社した時期については、本件制度について入社前に説明していた事実が立証されていないとして、投稿内容が反真実とまではいえないという判断をしています。
転職口コミサイトでは、投稿者の在籍期間も併せて口コミが投稿されることが多く、投稿内容の真実性の判断において、投稿内容がいつの時点の話なのかが問題になりやすいといえます。
ポイント&まとめ~名誉毀損の判断基準~
ポイント①名誉毀損に当たるには「社会的評価を低下させる」必要がある
名誉毀損が成立するためには、その投稿が単に気分を害するものであるだけでなく、客観的に企業の社会的評価を下げる表現であることが前提となります。ここでいう「社会的評価」とは、取引先・顧客・求職者など第三者から見たときに、その企業の信用や信頼が損なわれることを意味します。
例えば「この会社の商品は好みではない」という表現は、消費者個人の感想にとどまるため、社会的評価が直ちに低下するわけではありません。しかし、「この会社は不良品を多数販売している」「安全基準を守っていない」といった表現は、顧客や取引先に「信用できない企業だ」と思わせる効果を持ち、社会的評価を低下させる可能性があります。
また、投稿の性質によっては「意見論評型」と「事実摘示型」に分けられます。意見論評型は「味がまずい」「社内の雰囲気が悪い」など主観に基づく評価であり、一般に名誉毀損にはあたりにくいのに対し、事実摘示型は「残業代を払っていない」「ハラスメントが横行している」といった客観的事実の指摘であり、名誉毀損が成立しやすいとされています。
企業としては、投稿内容が「意見」なのか「事実」なのかをまず整理することが、対応を考える第一歩となります。
ポイント②投稿内容が「真実」であれば名誉毀損は成立しない
たとえ社会的評価を低下させる投稿であっても、投稿が公共の利害に関する事実で公益目的があり、かつ、その内容が真実である場合には、「真実性の抗弁」が成立し、違法とはされません。
裁判例でも、労務管理や取引実態など企業活動に関わる内容は「公共性・公益性」が認められることが多く、最終的に問題となるのは「その事実が本当に正しいのか(真実性)」という点です。例えば「サービス残業を強要している」という投稿があった場合、実際に未払い残業が存在すれば、その投稿は違法とまでは言えません。しかし、勤怠管理システムや賃金台帳などで残業代が適正に支払われていることを立証できれば、投稿は虚偽であり、名誉毀損の成立を主張できることになります。
企業として重要なのは、投稿内容が「反真実」(虚偽)であることを裏付ける証拠を備えておくことです。就業規則、労務管理の記録、取引契約書、社内調査報告などがその典型例です。逆に、日頃から証拠を残していないと、虚偽の投稿に対抗できないリスクが高まります。つまり、名誉毀損対策は「いざというときに証拠を出せる社内体制づくり」と直結しているのです。
ポイント③投稿に「具体的事実」があるかどうかが成否を分ける
裁判例をみると、名誉毀損が肯定された事案の多くは、投稿に具体的な事実の摘示があったケースです。例えば「残業代が支払われない」「社員を成果が出ないと2ヶ月でクビにする」といった表現は、企業の労務実態に関する具体的な事実を指摘しており、名誉毀損と認められる傾向にあります。
一方で、「担当者が酷い」「雰囲気が悪い」などの抽象的・感情的な記載は、具体的事実を摘示していないため、名誉毀損は否定されやすい傾向があります。裁判所も「企業の評判を下げるほどの具体性があるか」を重視しており、ここが明暗を分ける大きなポイントになります。
企業が対応を検討する際は、まず投稿の内容を冷静に読み解き、「具体的事実を摘示しているのか、それとも単なる感想か」を仕分けることが重要です。もし具体的事実の摘示があり、それが虚偽であると考えられる場合には、発信者情報開示請求や削除請求を前向きに検討すべきです。逆に抽象的な意見に過ぎない場合は、法的対応よりも広報対応や自社の改善活動によって評価を高める方が効果的なこともあります。
弁護士法人かける法律事務所のサービスのご案内
名誉毀損の成否は「社会的評価の低下」や「真実性の有無」といった法的な観点から判断されます。しかし、実際に自社がインターネット上で誹謗中傷の被害を受けたとき、「法的に名誉毀損に当たるのか」「どんな対応が可能か」を社内だけで判断するのは容易ではありません。
- 「会社名を特定してネガティブな投稿がされ、どう対応すべきか分からない」
- 「口コミサイトに事実無根の投稿があり、売上や採用に影響が出ている」
- 「発信者を特定して責任を追及したいが、名誉毀損になるのか判断できない」
- 「開示請求にはどの程度の時間やコストがかかるのか事前に知りたい」
このような悩みは、多くの企業で実際に寄せられているものです。
弁護士法人かける法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や風評被害から企業の信用とブランドを守るため、以下のようなリーガルサービスをワンストップで提供しています。
- 投稿削除請求(任意交渉・仮処分手続を含む)
- 発信者情報開示請求(裁判手続を通じた発信者の特定)
- 損害賠償請求・刑事告訴の検討
- 証拠保全や初動対応のアドバイス
多くのケースでは裁判手続が必要となるため、当事務所では 初動対応から証拠収集、手続の流れまでを丁寧にご案内し、安心してご依頼いただけるようサポートします。単なる法的手続の代行にとどまらず、「企業ブランドを守るパートナー」として、予防・体制構築の支援にも力を入れています。
インターネット上の誹謗中傷は、初動の速さが被害拡大を防ぐ最大の鍵です。状況に応じた最善の対応をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。