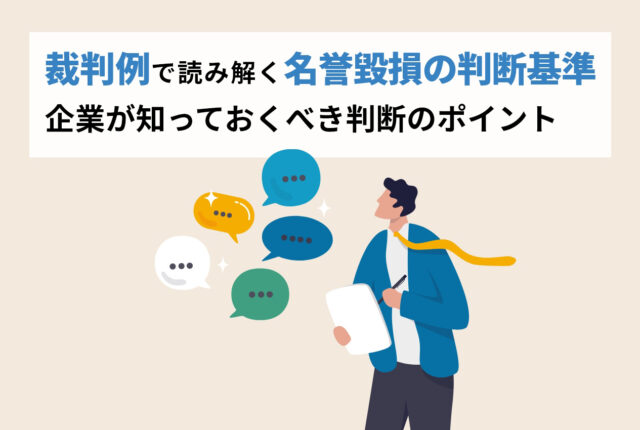目次
よくある相談
- X(旧twitter)で、当社が名指しで「ブラック企業」だと言われています。これは誹謗中傷だと思うので、開示請求をしたい。
- 飲食店の経営者ですが、Googleの口コミで「不衛生」と書かれてしまいました。今後の営業に悪影響を及ぼす可能性があるので、口コミを削除をしたい。
- 企業に対する誹謗中傷について、名誉毀損に当たるかどうかの判断基準を知りたい。
名誉毀損(名誉権侵害)とは?
民事上の名誉毀損は、他人の名誉権を侵害する行為であり、近時、インターネット上の投稿や掲示板への書込みにより発生する権利侵害として、代表的なものです。
名誉権とは、一般に、個人や法人が外部的に有している社会的評価のことをいい、この社会的評価を低下させる行為が、名誉毀損(名誉権侵害)になります。名誉権は、個人・法人を問わず有している人格的な権利(人格権)です。
社会的評価の低下とは?
名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為です。インターネット上の投稿でいえば、その投稿内容が、対象者の社会的評価を低下させる内容であることが必要になります。
社会的評価の低下の有無は、その記載内容について、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準として、対象者について悪い印象を与えるか否かによって判断されます(一般読者基準)。
社会的評価の低下については、以下の点が重要なポイントになります。
A 同定可能性の問題
「同定可能性」とは、投稿内容の対象者(その投稿が誰のことを言及しているのか)を特定できるかという問題です。ある投稿について、「同定可能性」がない場合、つまり、誰に対して言及しているのかわからない場合は、特定の対象者の社会的評価が低下したとはいえないため、名誉毀損には当たりません。
対象投稿に、社名やサービス名が記載されていない場合は、「同定可能性」が問題になることがあります。
*「同定可能性」の判断は、こちらの記事(Q&A<インターネット誹謗中傷対応>名誉毀損における同定可能性について、弁護士が解説します。)で詳細に解説しています。
B 事実摘示型と意見論評型
民事上の名誉毀損(名誉権侵害)には、大きく分けて①事実摘示型と②意見論評型があります。
①事実摘示型とは「○○株式会社は××という違法な行為をしている」といった、直接に事実を述べるものであり、②意見論評型とは「○○株式会社は、最悪の事業者である」といったように、事実ではなく意見を述べるものです。
名誉毀損(名誉権侵害)は、社会的評価を低下させるものであれば、事実摘示型でなく意見論評型でも成立する可能性があります。
もっとも、一般的には、意見論評型よりも事実摘示型の方が、名誉毀損として責任を追及しやすいため、対象投稿は事実摘示型と意見論評型のどちらに当てはまるかは、重要なポイントの一つです。
名誉毀損の正当化事由とは?
ある投稿内容について、対象者の社会的評価の低下が肯定され、名誉毀損表現に当たる場合でも、表現の自由(憲法21条)との均衡に鑑みて、一定の場合に、名誉毀損表現が正当化されることがあります。
名誉毀損表現の正当化事由としては、一般に、「真実性の抗弁(違法性阻却事由)」と「相当性の抗弁(責任阻却事由)」があります。
以下では、特に実務上で問題になりやすい「真実性の抗弁(違法性阻却事由)」について、詳しく説明します。
「真実性の抗弁」(違法性阻却事由)とは?
「真実性の抗弁」とは、以下のア~ウ(意見論評型の場合はア~エ)の要件を全て満たす場合に、名誉毀損表現の違法性を阻却するというものです。
- ア 公共の利害に関する事実に係ること
- イ 専ら公益を図る目的でなされたこと
- ウ 重要な部分の内容が真実であること
- (エ 論評としての域を逸脱したものでないこと) ※意見論評型の場合
これらの各要件を全て満たす場合、名誉毀損の違法性が阻却され、その投稿は違法ではないということになります。そのため、投稿者に対して、名誉毀損を理由とする責任追及ができないという結論になります。
※発信者情報開示請求の場合の注意点
インターネット上の投稿について、発信者情報開示請求を行う場合には、投稿による「権利侵害が明白」であることが法律上の要件とされている(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロパイダ責任制限法)5条1項1号)こととの関係で、実務上、開示請求者側が、当該投稿による社会的評価の低下に加えて、当該投稿に違法性阻却事由が存在しないことを主張立証する必要があります。
そのため、開示請求者側が、「真実性の抗弁」(違法性阻却事由)が成立しないこと、すなわち、
- ア 公共の利害に関する事実ではないこと
- イ 公益を図る目的でなされたものではないこと
- ウ 投稿内容が真実ではないこと(虚偽であること)
- (エ 人身攻撃等論評としての域を逸脱したものであること) ※意見論評型の場合
のいずれかに該当することを、主張立証する必要があります。
このうち、企業に対する名誉毀損についていえば、公共利害関連性(上記ア)や公益目的(上記イ)が否定されることは少ないため、実際には、投稿内容の反真実性(上記ウ)が問題になることが多いです。
そのため、開示請求者側としては、投稿内容が真実でないこと(虚偽であること)の説明や裏付けとなる証拠資料の提出について、十分に準備をしておく必要があります。
*事実摘示型と意見論評型での違い
民事上の名誉毀損には、大きく①事実摘示型と②意見論評型に分けられます。
投稿内容の反真実性(上記ウ)について、事実摘示型の場合は、摘示された事実についてのみ反真実を主張立証すれば足ります。
これに対して、意見論評型の場合は、その意見論評の重要な前提事実が反真実であることを主張立証する必要がありますが、前提事実が明確でないことも多く、広い範囲の前提事実について反真実の立証を求められることもあります。
そのため、一般的には、事実摘示型の方が投稿内容の反真実性を立証しやすく、開示請求が認められやすい傾向にあります。したがって、開示請求側としては、できる限り、事実摘示型として主張を構成する必要があります。
他方で、意見や論評については、表現の自由(憲法21条)の根幹を成すものとして厚く保護される観点から、一般的に、名誉毀損として開示請求が認められるハードルは高くなるといえます。
実際の裁判例の紹介
ここまで、特に企業に対する名誉毀損に焦点を当てて、名誉毀損の判断基準について説明してきましたが、実際に、企業に対する名誉毀損についての開示請求に関する裁判例を紹介します。
法人に対する名誉毀損を肯定した裁判例(東京地判令和2年12月24日)
【事案の概要】
インターネット掲示板において、原告(株式会社)に対して、従業員は「サビ残」をしており「かなりブラック」であると指摘する投稿が行われたため、原告が、名誉毀損を理由に、プロバイダに対して発信者情報開示請求を行ったという事案です。
【裁判所の判断】
上記事案において、裁判所は、以下のとおり述べて、原告に対する名誉毀損を肯定し、開示請求を認めました。
「本件投稿は、原告の従業員が「サビ残」をしており「かなりブラック」と指摘しており、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすると、原告ではサービス残業(本来支払われるべき残業代が支払われない時間外労働(残業)のこと)が横行しており「ブラック」企業(労働基準法を遵守せず違法な労務管理を行っている会社)であるという印象を与えるものといえ、原告の社会的評価を低下させ名誉権を侵害するものである。」
「この点、本件投稿を行ったIPアドレスにかかる契約者からの回答書によれば本件投稿の内容は、少なくとも投稿者の友人の経験を踏まえた評価として真実であるとのことである。しかしながら、かかる回答内容を具体的かつ客観的な証拠があるともうかがうことができない。他方で、原告ではセキュリティカードにより入退館時刻を管理し、オンラインで出退勤時刻を記録した上で、誤差が1月3時間以内(1日10分程度)となるよう指導しているとのことであるから、仮に原告においてサービス残業が1、2件あったとしても、「かなりブラック」といえるほどのサービス残業が横行しているとは認められない。また、本件投稿者において友達の話を真実と認めるに足りる相当な理由があるとも認められない。」
【コメント】
「ブラック」「ブラック企業」という言葉は、今となっては一般的な用語として確立した言葉といえますが、解釈の余地もある抽象的な言葉であり、その意味が必ずしも明確といえるものではありません。
この事案では、「ブラック」という指摘の他に、「従業員が「サビ残」をしている」というある程度具体的な事実の指摘を含んでいたため、「サービス残業(本来支払われるべき残業代が支払われない時間外労働)が無いこと」を立証の対象にすることで、投稿内容の反真実性を基礎づけることができたものといえます。そのため、「従業員が「サビ残」をしている」という事実の指摘があったことが、ポイントといえます。
仮に、「従業員が「サビ残」をしている」という指摘がなく、単に「ブラック」という指摘だけであった場合、社会的評価の低下自体が否定されたり、仮に社会的評価の低下は肯定されても、投稿内容の抽象性から虚偽性の立証が困難となり、開示が否定される可能性が高まっていたと考えられます。
法人に対する名誉毀損を否定した裁判例(東京地判令和3年1月19日)
【事案の概要】
Googleマップの口コミで、原告(有限会社)に対し、星5つ中1点の評価を付けた上で、「不衛生で、従業員の態度も悪い、底辺で残念な印象を受ける」という内容が投稿されたため、原告が、社会的評価の低下による営業権の侵害を理由に、プロバイダに対して発信者情報開示請求を行ったという事案です。
【裁判所の判断】
上記事案において、裁判所は、以下のとおり述べて、開示請求を認めませんでした。
「本件投稿は、原告について「不衛生」との文言を用いているものの,そもそも「衛生」・「不衛生」は多分に評価を含む概念である上、「不衛生で従業員の態度も悪く底辺な残念な印象を受けました。」との文章を素直に読めば、投稿者における「印象」を口コミとして記載したものにすぎないことは明らかであり、本件投稿上、不衛生であると投稿者が考えた具体的な根拠(事実)を窺わせるような記載もない。
そうすると、本件投稿は、「従業員の態度が悪い」、「底辺な残念な印象」などの記載も含め、そもそも事実を摘示したものとはいえず、かつ、特定の事実を基礎とした意見ないし論評にすら至らない、純然たる意見ないし論評にとどまるというべきである(したがって、真実性は問題とならない。)。」
「それを前提として、まず、名誉棄損として社会から受ける客観的価値を低下させるかを検討するに、「衛生」との用語には、辞書的には「健康の保全・増進をはかり、疾病の予防につとめる」との意味があることは認められるものの、一般人が「Googleマップ」の口コミを閲覧した際に、そのような辞書的な意味合いで記載されたものと捉えることは考え難く、単に投稿者が主観的な評価を意見ないし論評として記載したと捉えるのが通常である。
そうすると、原告のように多数の取引先や顧客を相手に商売をする業者において、多数に及ぶ取引先や顧客等の中には、原告の提供するサービス、価格又は対応などに不満を持つ者も含まれることはむしろ自然であるから、このような不満を持つ者がいるということ自体が原告の社会から受ける客観的価値を当然に低下させるかは疑義がある。」
「口コミ情報は、当該事業者の良い情報や悪い情報を集積することにより、「Googleマップ」を閲覧する一般人が当該事業者の利用を選択するか否かの一助になるものとして、一般人の知る権利に資するものである。広く事業を行っている者は、広く事業を行う帰結として、原則としてそのような外部からの主観的な批判・不満などの評価を受けることは甘受すべきであるから、当該事業者にとって不服のある内容(いわゆる悪い口コミ)が記載されている場合であっても、それが口コミ情報投稿者の主観的な批判・不満といった意見ないし論評にとどまる限りは、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しているなどの場合を除き、その公共性・公益性に鑑みて、名誉毀損の不法行為には当たらないと解するのが相当である。
その見地で本件投稿をみるに、「底辺」という言葉はやや強い表現ではあるものの、「不衛生」、「残念」、「印象」などの表現全体をみれば、投稿者における主観的な批判・不満にとどまり、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱しているとはいえない。」
【コメント】
インターネット上の口コミには、具体的な事実の指摘は伴わないものの、事業者に悪印象を与える内容の投稿が多く、このような投稿について、名誉毀損に当たるかがよく問題になります。
本件事案のように、具体的な事実の指摘がなく、個人の主観や感想、意見にとどまるような投稿の場合は、そもそも社会的評価の低下が否定されることも多くあります。その意味で、投稿の削除請求や開示請求を検討する上では、やはり、投稿に具体的な事実が摘示されているかという点が、重要となります。
ポイント~投稿の削除・開示の判断基準~
① 投稿が名誉毀損に当たるための条件とは?
インターネット上の投稿が名誉毀損になるには、 「一般の人が見たときに、企業の社会的評価が下がる内容であること」が必要です。また、投稿の内容は大きく次の2つに分類されます。
- 事実摘示型(例:「従業員にサービス残業をさせている」などの事実の指摘)
- 意見論評型(例:「ブラック企業だと思う」などの評価・感想)
② 投稿が真実なら名誉毀損にならない場合がある
たとえ対象者の名誉を毀損する内容であっても、その内容が「事実であり公益目的で書かれたもの」と認められれば、「真実性の抗弁」により違法とはされず、名誉毀損は成立しません。
企業が発信者情報の開示を請求するには、投稿内容が虚偽(=真実でない)であることを具体的に主張・立証する必要があります。
③ 投稿に「具体的な事実」があるかが重要な分かれ目
- 「事実が書かれている投稿」→ その事実が虚偽であることを証明できれば、開示請求が通りやすい。
- 「ただの主観や感想」→ 社会的評価の低下とは言えないと判断され、開示が認められにくい。
企業に対する誹謗中傷への対応では、「どのような内容が書かれているのか(事実か、意見か)」をまず丁寧に見極め、反論資料や客観的な証拠をそろえることが、開示請求を成功させるポイントになります。
弁護士法人かける法律事務所のサービスのご案内
弁護士法人かける法律事務所では、企業に対するインターネット上の誹謗中傷に対応するため、投稿削除の請求、発信者情報の開示請求、損害賠償請求など、状況に応じた最適なリーガルサービスを提供しています。
- 「会社名を挙げて『ブラック企業』と書かれたが、どう対応すべきか分からない」
- 「口コミサイトに事実無根の投稿があり、売上や採用に影響が出ている」
- 「発信者を特定して責任を追及したいが、名誉毀損になるのか判断できない」
- 「開示請求にはどの程度の時間やコストがかかるのか事前に知りたい」
こうした企業様のご不安やお悩みに対し、豊富な対応実績をもとに、法的観点から明確な解決策をご提案いたします。
発信者情報開示請求や削除請求の多くは、裁判手続が必要となるため、企業様には、初動対応・証拠収集・手続の進め方などをわかりやすく丁寧にご案内し、安心してお任せいただけるよう全力でサポートいたします。
当事務所では、「安心を提供し、お客様の満足度を向上させる」という行動指針(コアバリュー)を掲げ、単なる法的手続の代行にとどまらず、企業ブランドを守るパートナーとしての役割を重視しています。
まずはお気軽にご相談ください。状況に応じた最善の対応をご提案いたします。