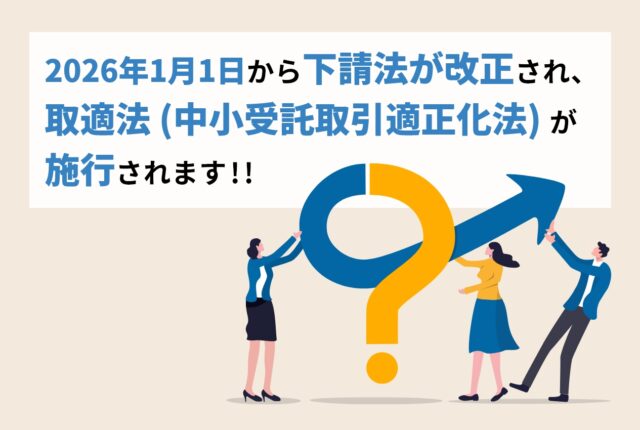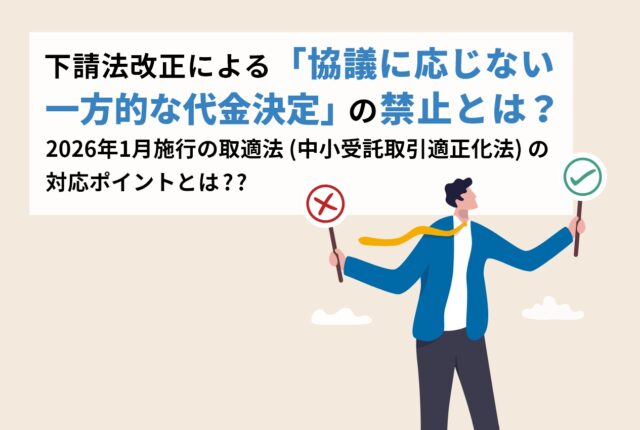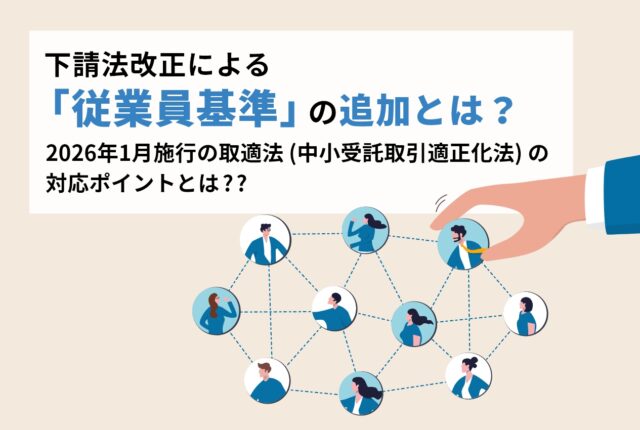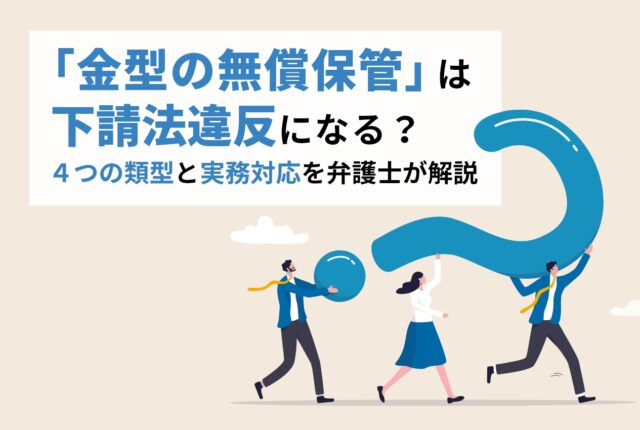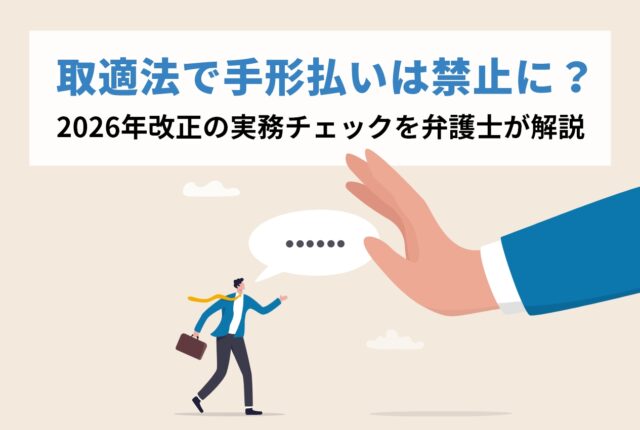目次
よくある相談
- 特定運送委託とはどのような取引を指すのですか?これまでの下請法と何が違うのでしょうか?
- 自社が委託する運送業務が「特定運送委託」に当たるかどうか、どのように判断すればよいですか?
- 特定運送委託が追加されたことで、委託事業者として新たに負う義務や注意点はありますか?
取適法(中小受託取引適正化法)とは?
近年、労務費・原材料費・エネルギーコストが急激に上昇する中で、発注者と受注者が対等な関係を築き、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁を定着させる、いわゆる「構造的な価格転嫁」の実現が求められています。
こうした状況を踏まえ、受注者に一方的な負担を押しつける商慣習を是正し、取引の適正化と価格転嫁の徹底を図るため、下請法が改正され、2026年1月1日から取適法(中小受託取引適正化法)が施行されることになりました。
この改正に伴い、下請法に関連する法律の題名や用語が以下のとおり、変更されます。
- 下請代金支払遅延等防止法(略称:下請法)
→製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法) - 下請代金
→製造委託等代金 - 親事業者
→委託事業者 - 下請事業者
→中小受託事業者
取適法は、製造委託等に関し、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによって、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを目的としており、委託事業者の義務や禁止行為を規定しています。
委託事業者の義務には、①中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等、②書類の作成・保存義務、③製造委託等代金の支払期日を定める義務、④遅延利息の支払義務があります。
取適法の適用対象
取適法では、取適法の対象となる取引(中小受託取引)に関し、①取引内容と②資本金基準又は従業員基準によって判断されます。
対象取引(中小受託取引)に該当する場合、委託事業者は、優越的地位にあるものとして取り扱われ、取引に際して様々な行為を規制されることになります。
そのため、取適法を検討する上では、取適法の対象となる取引(中小受託取引)の該当性を判断することが重要なポイントとなります。
取引内容の種類:
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
- 特定運送委託(←改正によって追加)
*従業員基準の追加の詳細は、こちら
取適法の適用対象の拡大~特定運送委託の追加~
改正前の下請法では、発荷主(メーカーや卸売業者等)が運送事業者に対して行う運送委託は、直接の規制対象外でした。この分野は「独占禁止法の物流特殊指定」によって対応されていましたが、現場では依然として問題が残っていました。具体的には、立場の弱い運送事業者が、荷役や荷待ちを無償で強いられるなど、不当な取引慣行が深刻化していたのです。
こうした背景を踏まえ、2026年1月施行の取適法では、新たに「特定運送委託」という類型が追加されました。これにより、物品の販売・製造・修理、または情報成果物の作成に伴って必要となる運送を、他の事業者に委託する取引が対象となります。
つまり、製造や販売などの「目的物の引渡し」に不可欠な運送の委託も、製造委託や修理委託と同様に取適法の規制対象に含まれることになり、委託事業者の義務や禁止行為が適用されることになります。
この改正により、発荷主と運送事業者の間で行われる取引が法の保護下に置かれることで、不当な負担の押し付けや価格転嫁の不徹底といった問題に歯止めをかけ、中小運送事業者の取引環境を改善することが期待されています。
特定運送委託の具体例
「特定運送委託」とは、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託をいい、具体的には、事業者が販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品等について、その取引相手方に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいいます(取適法2条5項)。
類型①:
物品の販売事業者が、その物品の販売先に対する運送を他の事業者に委託する場合
→具体例:家具小売業者が、販売した家具を顧客に引き渡す場合に、その家具の運送を他の事業者に委託すること
類型②:
物品の製造を請け負う事業者が、その物品の製造の発注者に対する運送を他の事業者に委託する場合
→具体例:精密機器メーカーが、製造を請け負い完成させた精密機器を顧客に引き渡す場合に、その精密機器の運送を他の事業者に委託すること
類型③:
物品の修理を請け負う事業者が、その物品の修理の発注者に対する運送を他の事業者に委託する場合
→具体例:自動車修理業者が、修理を請け負い完成させた自動車を顧客に引き渡す場合に、その自動車の運送を他の事業者に委託すること
類型④:
情報成果物の作成を請け負う事業者が、その発注者に対する運送を他の事業者に委託する場合
→具体例:建築設計業者が、作成を請け負い完成させた建築模型を顧客に引き渡す場合に、その建築模型の運送を他の事業者に委託すること
取適法2条5項
この法律で「特定運送委託」とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
特定運送委託の追加が実務に与える影響
① 委託事業者の義務・禁止行為の適用
特定運送委託が取適法の対象に追加されたことで、荷主(委託事業者)も製造委託等と同様に、運送事業者との関係において、発注内容の明示義務、書類の作成・保存義務、支払期日の設定義務、遅延利息の支払義務を負うことになります。
また、受領拒否、支払遅延、代金の減額といった禁止行為も規制対象となるため、従来の運送委託における慣行についても、法令違反とならないか確認が必要となります。
② 運送実務における取扱いの見直し
これまでの運送実務では、長時間の荷待ちや荷役作業の無償対応、従業員派遣の要請、税金等の立替えといった取引慣行が存在していました。特定運送委託が規制対象となったことにより、これらの行為が不当な負担として問題となる可能性があります。
そのため、契約条件や発注手続において、待機時間や追加作業の有償化、立替費用の取扱いを明確にし、実務に反映させることが求められます。
③ 適用範囲の拡大への対応
従業員基準の導入と併せて特定運送委託が追加されたことで、取適法の適用範囲は大幅に広がりました。これまで自社には関係がないと考えていた企業であっても、委託内容や取引相手の規模によっては対象となる可能性があります。
「知らなかった」「対象外だと思っていた」では免責されず、違反リスクを避けるためには、早期に社内の確認体制や契約書の整備を行うことが必要です。
よくある質問~特定運送委託の追加~
① 特定運送委託の対象範囲はどこまで含まれますか?
特定運送委託とは、販売・製造・修理または情報成果物の作成における取引の相手方(又はその指定先)に対する引渡しに必要な運送を、他の事業者に委託するものを指します(取適法2条5項)。
運送の行為が対象であり、荷積み・荷下ろし・倉庫内作業などの附帯業務のみは含まれないと解釈されます。該当するかどうかは、契約や発注内容をもとに判断する必要があります。詳細は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」を確認する必要があります。
② 委託事業者が負う義務は具体的に何ですか?
特定運送委託に取適法が適用される場合、委託事業者は、4つの義務を負います。
- 発注内容等を明示する義務(発注に当たって、発注内容【給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法】等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示すること)
- 書類等を作成・保存する義務(取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成し、2年間保存すること)
- 支払期日を定める義務(検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めること)
- 遅延利息を支払う義務(支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息(年率 14.6%)を支払うこと)
③ 中小受託事業者が同意していれば、取適法違反にはなりませんか?
たとえ受託側(運送業者)が同意していたとしても、また委託事業者に違反の認識がなかったとしても、取適法違反となり得ます。取適法は契約自由の原則に優先するため、従来の慣行や相手方の了承を理由に違反を正当化することはできません(中小受託取引適正化法ガイドブック14頁参照)。
そのため、同意の有無にかかわらず、委託事業者は法令に沿った取引条件を整備する必要があります。
弁護士法人かける法律事務所における取適法対応のサポート
2026年1月の改正により、取適法の規制対象や禁止行為は、広がります。発注者・受注者の双方にとって「どこまで対応が必要か」「契約書や社内体制をどう変えるべきか」を早めに整理しておくことが重要です。
弁護士法人かける法律事務所では、以下のようなサポートを提供しています。
① 契約書・取引スキームのリーガルチェック
- 改正後の「従業員数基準」や「特定運送委託」の追加などを踏まえ、自社が規制対象となるかを判定。
- 委託契約書や基本契約の内容を精査し、禁止行為(協議に応じない一方的な価格決定、手形払等)に抵触しない条項へ修正。
- 実際の取引スキームが取適法に沿っているかを検証し、改善提案を行います。
企業のメリット:
- 不意に「法違反リスク」を抱えることを防ぎ、安心して取引を継続できます。
② 価格交渉・価格転嫁の実務サポート
- コスト上昇分を価格に反映するための「協議の進め方」について、法的観点からアドバイス。
- 発注者側企業には、受注者からの協議要請にどう対応すべきか、社内ルール作成を支援。
- 下請代金の引下げやコスト上昇における引上げ価格の検討・プロセスについて、法的観点からアドバイス。
企業のメリット:
- 法に沿った適正な交渉ができ、長期的に安定した取引関係を構築できます。
③ 社内研修・コンプライアンス体制の構築
- 経営層・購買担当者向けに「取適法対応セミナー」を実施。
- 違反事例や実務上のリスクを共有し、現場担当者が実践できるチェックリストを提供。
- 法改正に合わせた社内マニュアル・ガイドラインの整備もサポート。
企業のメリット:
- 現場の担当者レベルまで法改正の理解を浸透させ、違反リスクを未然に防止できます。
独占禁止法・下請法対応は、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
紛争やトラブルを未然に防止し、健全な企業体質をつくって、経営に専念できる環境を整備するためにも、顧問契約サービスの利用について、是非、一度、ご検討ください。
顧問契約サービスでは、独占禁止法・下請法対応もリーズナブルに、かつ、迅速に対応できます。コンプライアンス研修(独占禁止法・下請法)も引き受けています。